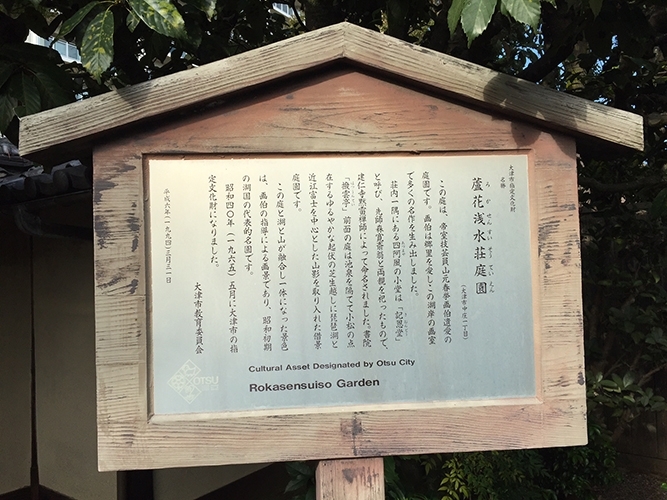修善寺
山間を利用した広い借景の庭に、
池や滝を作り作庭された見事な庭に盆栽を飾って
国内外のお客様に好評をいただいています。
色々なメディアにも取り上げられ
先日も人気のドラマのロケ地にも使われた様です。
「宙sora」HP
http://www.kinryu.net/html/
年々、庭の盆栽が増えていってます。
池や滝を作り作庭された見事な庭に盆栽を飾って
国内外のお客様に好評をいただいています。
色々なメディアにも取り上げられ
先日も人気のドラマのロケ地にも使われた様です。
「宙sora」HP
http://www.kinryu.net/html/
年々、庭の盆栽が増えていってます。